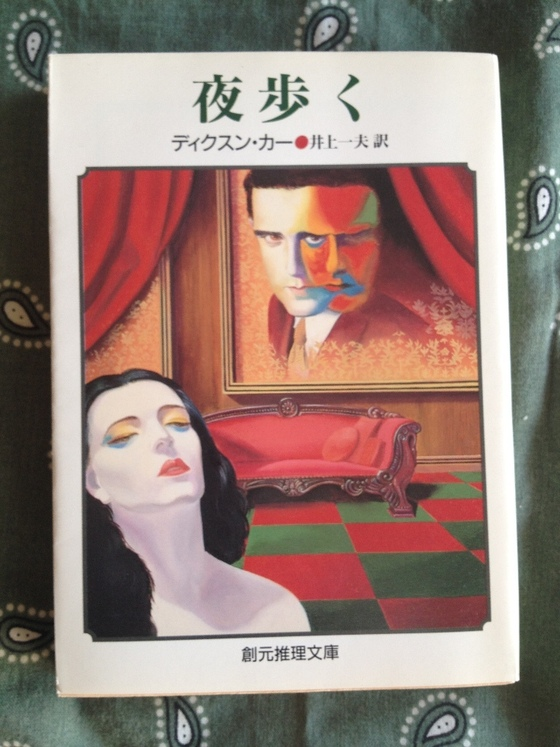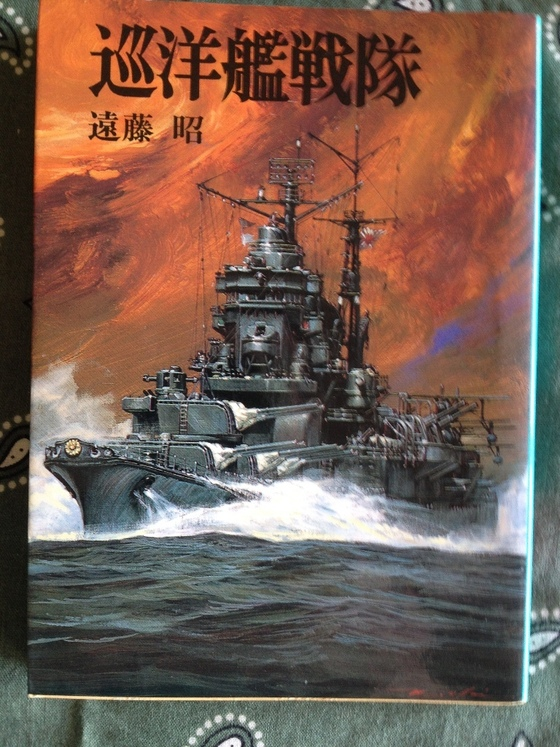今年6月に行ったローマ旅行が大変良かったので、只今二度目のローマ旅行を企画中である。カタール航空のビジネスクラスも良かったけれど、6泊テルミニ駅前のホテルに泊まって1週間有効の市内交通乗車券で方々歩き回った。
https://nicky-akira.hatenablog.com/entry/2019/07/04/140000
今度はローマで何しようかな、などとノー天気なことを考えながらBook-offを冷やかしていて、見つけたのが本書。1999年の書下ろしと、ちょっとガイドブックとしては古いが、前書きにもあるように「ガイドブックではありません」とのことだから買ってみた。

内容は決して初心者向きのものではなく、旅行社は使ってもこれに振り回されるのではなく、逆に使い倒すくらいの準ベテランが読んで役に立つレベル。普通の本は最初から読むのだが、この手のものは目次を見て知りたいところからページを開ける。フライトや市内交通については割合分かっているので、今回はレストランなどでの食事。やはり参考になる記事が載っていた。
・ワインは地元のテーブルワインで十分
・パスタを「メッゾ!」と言って半分にしてもらうこと
・並みいる料理店の中では、安いほど美味しい
最初の件は、実際トリノに仕事で行った時の、おひとり様ディナーで経験したこと。地域性の国イタリアでは、地元のものが一番うまい(コスパがいい)のだ。次のは、前菜・パスタ・メインと食べきれない時のウラ技というわけ。これなら最後までいけそうだ。最後のはちょっとマユツバだが、今度試してみてもいいだろう。
あと役に立ったのは、8月が普通の都市ホテルは「ローシーズン」だということ。みんなリゾ-トに出掛けてしまうので、都市は閑散としているという。また日曜日が(聖なる日なので)シャッター街になるというのはわかるのだが、月曜日の午前中もその傾向が強いということ。二日酔いなのかね、と思う。滞在時必要なものは土曜日、できれば金曜日のうちに買い込んでおいた方がいいということだ。
少し勉強になったので、他の部分も読んで頭に入れてから次のローマ旅行を考えることにします。