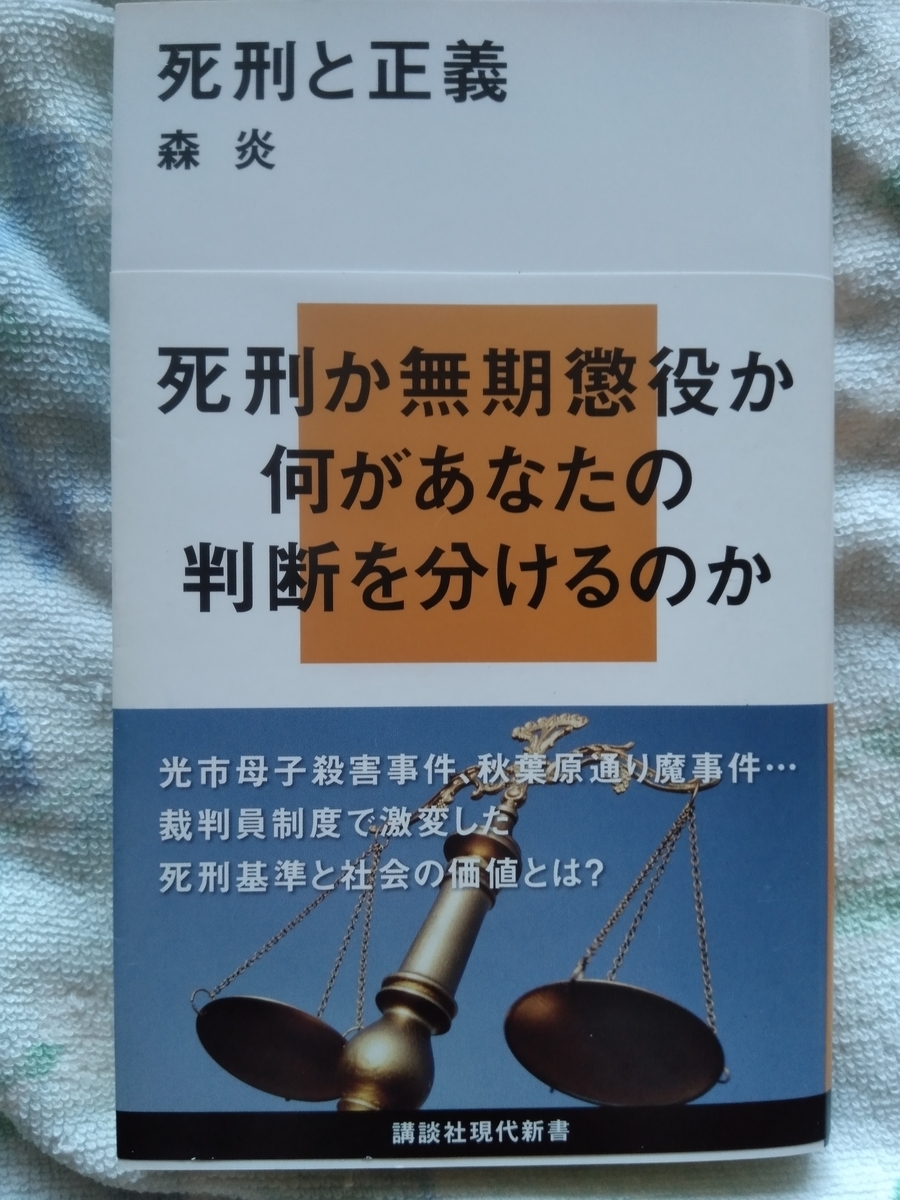このブログで「雑誌」を取り上げるのは始めて。週刊誌など、昔は<週刊ベースボール>を買っていた時期もある。空港のロビーなどで<週刊文春>を読むこともあったが、このところはまったくご無沙汰。それなのになぜ<日経ビジネス>を取り上げるかと言うと、日経さんから本書が送られてきたから。7/4付けの同誌は「経済安保とは何か~分断する世界で生き残る知恵」と題して、特集が今般成立した経済安全保障推進法についてのもの。
この特集に少し協力をしたので、出版元から送ってもらったのだ。別ブログでも、この法制について何度かコメントさせてもらっている。本来は「Economic Statecraft」のはずなのに、法案が「産業政策」になっているのではと苦言を呈した。
「Economic Statecraft」って?(前編) - Cyber NINJA、只今参上 (hatenablog.com)
さて本書の特集だが、中心となる記事は4つ。
・推進法の紹介と先送りされた課題(データや人権の保護)
・サプライチェーンリスク(権威主義国、気候変動、自然災害、労働人口等)
・喫緊の3テーマ(エネルギー、食料、技術&人材)

加えて4人の専門家が、それぞれの立場で経済安保の論点をコラムで述べている。
・サイバー攻撃からのウクライナのインフラ防御(慶応大学教授)
・経済はそもそも安全保障の柱(内閣特別顧問)
・サイバーセキュリティ対策のカギは中小企業(シンクタンク代表)
・企業の協力を得るには説明と補償が必要(東京大学教授)
主張の多くは産業政策に矮小化してはいけないというものに見えた。加えて特集外だが、コロンビア大のスティグリッツ教授の記事「ダボス会議に見た変節~グローバル化は衰退する」が興味深かった。今年のダボス会議は失敗だったとした上で、
・市場はリスクの値付けをうまくできていない
・グローバリゼーション推進は欠陥のある超楽観主義だった
・それに対する反省もないダボス会議は、40年間世界経済の舵取りを誤った
・資本主義は寡占化の傾向があり、ダボス会議により独占が進んで社会が脆弱になった
と手厳しい。世界が分断された結果、リスクの値付けが上手くいけばいいのですが。