2012年発表の本書は、東京地裁などの裁判官を経験して現在は弁護士である森炎氏の著書。裁判員制度施行後3年経ち、死刑判断に変化が出ていることを論考したもの。有罪・無罪だけではなく、量刑まで裁判員が決めなくてはならない。死刑判決を下すにあたり、裁判員には職業裁判官より多くの心理的ハードルがあると思われる。
帯にあるように「何が死刑と無期懲役を分けるのか」について、裁判員制度以前の基準が20ほどの実例とともに紹介されている。基準の最大のものは、犠牲者(殺した人)の数であり、続いて金銭目的か計画的かが問われる。
◆犠牲者3人以上
94%の確率で死刑。無期懲役となったケースはいずれも金銭目的ではなかった。
◇犠牲者2人
金銭目的のあるケースでは、死刑率81%。そうでないケースでは51%。
■犠牲者1人
ほぼ無期懲役だが、凶悪な犯罪と認められたケースでは死刑があり得る。
ここでいう凶悪な犯罪とは、計画的でかつ金銭目的なもの。具体的には、
・身代金目的誘拐殺人
・保険金殺人
・強盗殺人
の3つがあるという。このような基準に対して、減刑の方向に動く要素もいくつかある。
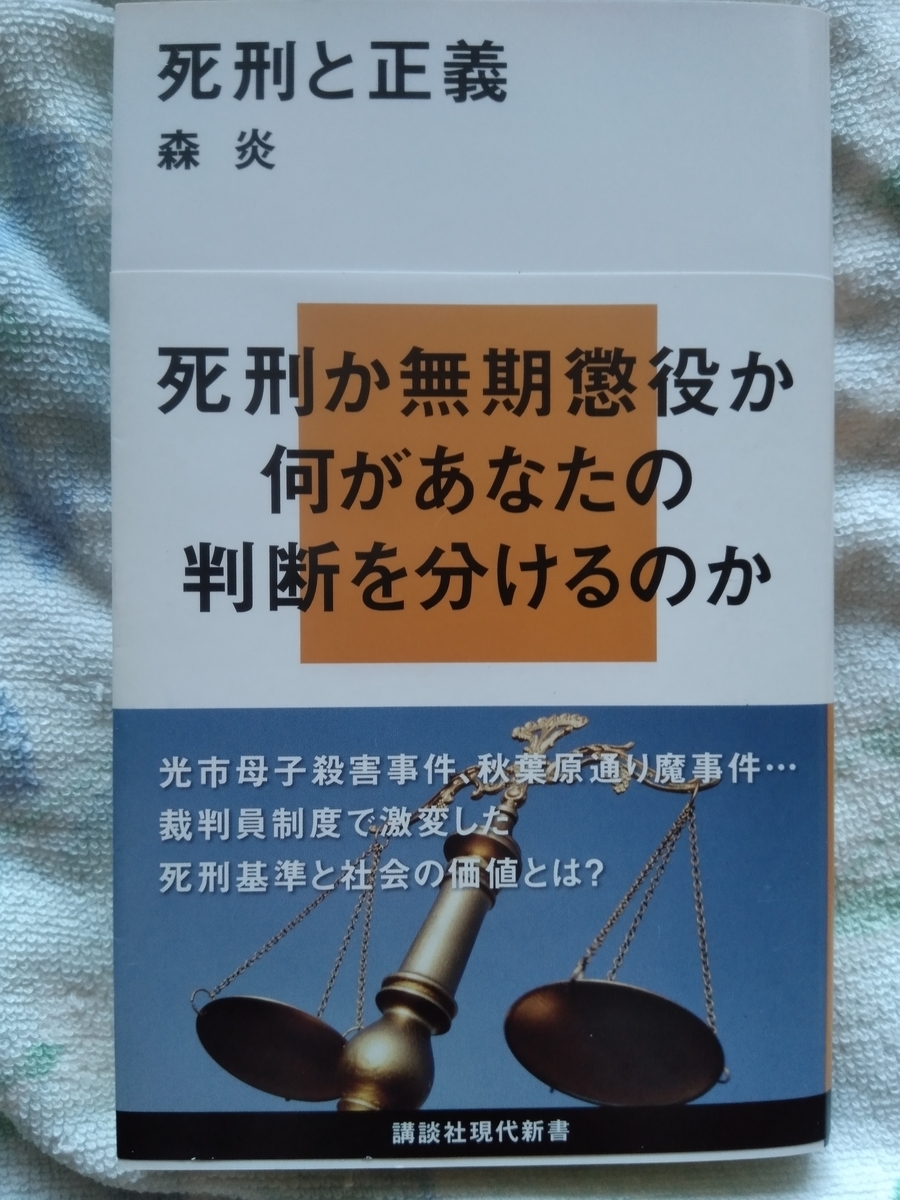
まず被告人の恵まれない環境、「無知の涙」で有名な永山死刑囚のようなケースだ。社会全体が被告人を追い詰めて犯罪を犯させたとの判断で、減刑される可能性がある。もちろん弁護人はその点を強調して、死刑判決を回避しようとする。
続いて閉じられた空間での殺人、要するに家族内での殺し合いだ。無理心中のようなケースもある。その場合は、死刑にすると無理心中を完遂させることになるとの反対意見も出てくる。さらに心神耗弱ではなかったかや責任能力の有無についての判断、未成年の犯罪についてはどうか等々、死刑と無期懲役を分ける判断は、すでに法律論ではないと著者は言う。
そこで問題となるのは、このような「常識」をもっている職業裁判官ではなく、一般市民が量刑を決めるという制度の運用である。本書発表の時点で3年しか経っていない裁判員制度だが、「犠牲者一人でも死刑」の判決が多くなっているという。戦後の混乱期を除いて年間10件ほどの死刑判決だったものが、このまま増えると年間20~50件になるのではと筆者は警告する。
とはいえ、本書のすべての事例で一審で結審したケースはありません。プロ裁判官が裁く二審以降があるから、その点は心配いらないと思いますが。