ジャック・ヒギンズの諸作は、第二次世界大戦終盤を舞台にした「鷲は舞い降りた」「鷲は飛び立った」から現代まで、連綿と続く大河ドラマのようなものだ。「鷲は舞い降りた」でチャーチル誘拐を狙うドイツ将校シュタイナー少佐を助けたIRAの闘士リーアム・デヴリンが、本書でも活躍する。
東西冷戦が始まっていた1959年、ウクライナの田舎町にKGBが作った特殊なエリアがあった。そこでは住民は英語を話し、ポンド紙幣で買い物をしている。イギリスに派遣するスパイの養成場なのだ。20歳のケリイはロシア人とアイルランド人の混血、すでに両親は亡くなっている。
ケリイは訓練の途中、逮捕しようとした警官(に扮した俳優)を所持を許されていない拳銃で射殺する。俳優の娘タニヤはケリイの顔を目に焼き付けた。叱責はされたものの試験に合格したケリイはアイルランドに派遣される。IRAと英国政府の軋轢をあおり、英国の国力を弱めるのが目的。
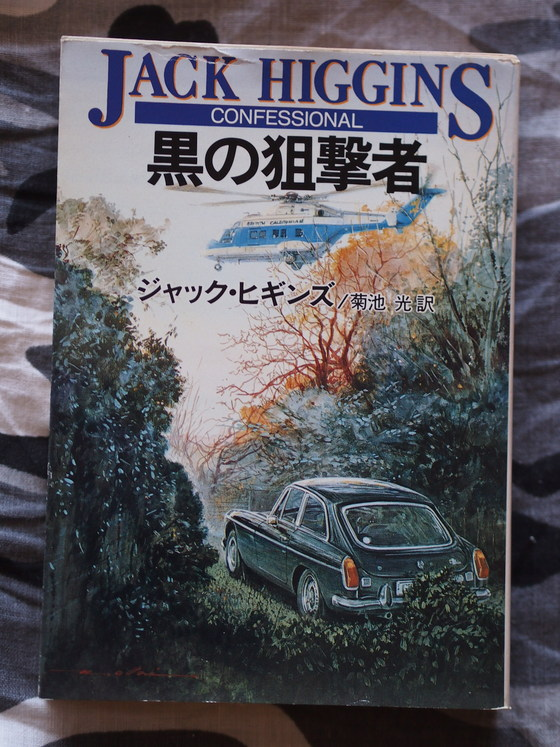
1982年、ケリイはクセイン神父と名乗り、デヴリンの隣人として20年近い交流を続けていた。イギリスはフォークランド紛争の只中にあり、戦況が刻々と「ダウニング街」に伝えられてくる。そんな中、IRAにつながる人物が射殺され情報機関の長ファーガスン准将は、IRAからみで年間1~2件の暗殺事件がありIRAとの宥和がそのたびに頓挫していることに気づく。
ファーガスン准将はデヴリンらの協力を得てKGBのスリーパーの正体に迫るが、デヴリン邸を盗聴しているケリイはイギリス情報部のウラをかいて自分につながる証人を消してゆく。しかし国際的なピアニストとして成長したタニアがデヴリンのところに来たことを知った彼は、最後のミッションを果たそうとカンタベリーへ向かう。狙いは、イギリスを訪れる教皇の暗殺。
まるで「ゴルゴ13」のようなケリイは、官憲や情報部の追跡をかわし死を偽装もする。しかしデヴリンは「こいつに限っては自分で死体を見るまで(死を)信じない」とつぶやいて、追及の手を緩めない。その間にもケリイは途中で暴漢から助けたジプシーの少女と一緒に、一歩一歩カンタベリーに近づきつつあった。
ヒギンズの全ての作品に言えるのだが、クラシックな中にも圧巻の迫力がある。ケリイも全く血の通わない暗殺機械ではなく、関わり合いになる必要のない少女を助けたりして官憲に正体を捉まれる愚を犯す。そもそも、タニアとデヴリンを殺す機会もあって、そうしていればスリーパーとしてのカバーはもう少しもったはず。人間善もすれば悪もする、というのは池波正太郎の史観ですが、本書にもそういうテイストを感じました。